
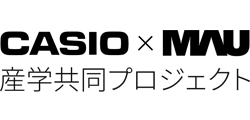
PRESENTATION 発表
PRESENTATION 発表
子どもたちと共に生きる
[取材先 ]児童養護施設れんげ学園 石井 真一さん/出村 真慈さん/下釜 穣さん
[チーム] グレーグレイス イ ダビン/川﨑 風香/宮本 悠帆/村松 知明
私たちは、自分自身や身近な人が目に見えないハードルを持っていることで、発達障害やグレーゾーンというものに興味を持ちました。れんげ学園さんの取材進めていく中でテーマを変えていき、チーム名は「グレーゾーン」の「グレー」と「グレイス」を合わせました。

テーマについて
川﨑 私たちは「子どもたちと共に生きる」をテーマに取材を行ってきました。
まず、一つ皆さんにお聞きしたいことがあります。皆さんには信頼できる人はいますでしょうか。いろんな答えが出ると思うんですけれども、まず一つ、家族や友達というのが挙げられると思います。
今回、私たちが取材を行いました児童養護施設れんげ学園さんでは、いろいろな事情で家族と暮らせなくなった子どもたちが生活しております。
例えば、虐待を受けてしまったりとか、何かトラウマを抱えてしまったり、大人を信頼できなくなってしまった子どもたちです。このような、心に傷を負い、ハードルができてしまった子どもたちが私たちのまわりにいたとして、私たちはどのように接すればよいのかということを考えて取材を行ってきました。
取材の目的
取材の目的は、まず私たちが児童養護の実態を知るということ、そしてそれを皆さんや社会にどう伝えることができるのか、私たちはどのように向き合うことができるのかということを目的としています。
次にもう一つ質問を皆さんにしたいと思います。
イ 皆さんは、親と暮らせない子どもがどれくらいいるか知っていますか。
答えは、約4万2000人です。この中で虐待の経験がある子どもたちが 71.7%、そして何らかの障害がある子どもたちが 42.8%で、外的、内的にもさまざまなハードルを抱えています。
保護者がいない、虐待されている、そのほか。養護を要する児童と暮らし、自立の援助を行う施設が児童養護施設です。
全国に610カ所あり、東京に60カ所あります。その中で私たちが取材を行ったところが、児童養護施設れんげ学園です。

宮本 れんげ学園は 1979年に開園し、2歳から18歳までの52人の子どもたちが47名の職員さんと共に暮らしています。
れんげ学園では支援の幅を広げるために新しい取り組みにも挑戦しています。
まずは不登校の子どもたちのための居場所づくり、居場所事業ぶらんこです。学校に行きづらい子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供し、次の一歩を踏み出せるエネルギーをためる時間づくりを支えています。
ほかにも、保護者の方が病気や出産などで子どもを養育できない期間に施設で一時的にお子さんを預かるショートステイという取り組みも行っています。
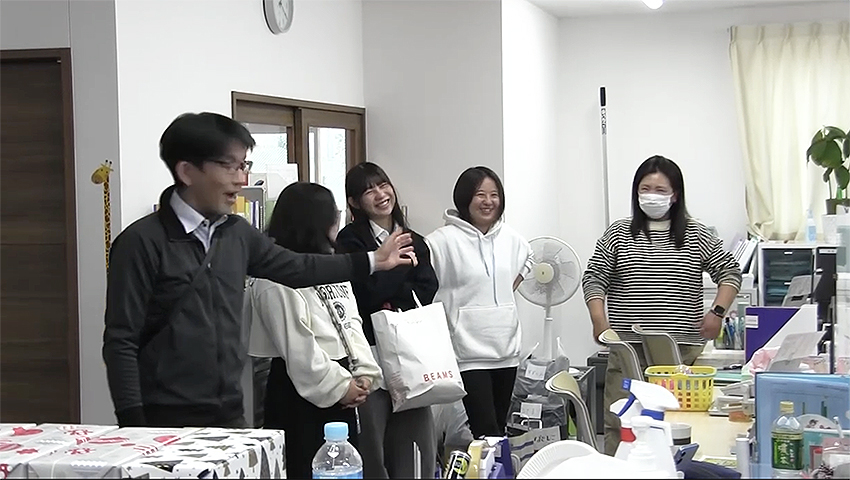
取材に伺った際、私は、職員さんどうしがとてもいい信頼関係を築いているなと感じました。
その理由をお聞きすると、コミュニケーションの幅を広げる取り組みとして、一つの簡単なテーマを職員さんどうしで話し合う時間が毎週設けられていました。
職員さんどうしの関係の良さが情報共有を円滑にし、元気の良さが子どもたちに良い影響を与えるそうです。その話し合いに私たちも参加させていただき、「子どもの頃憧れていたもの」というお題について話し合いました。
ディスカッション
村松 ここからはディスカッションと題しまして、子どもたちとの共生についてお話ししていければと思います。
本日はれんげ学園さんより 3名の職員さんに来ていただきました。どうぞこちらにお越しください。(拍手)
では、一つ目の質問に早速移っていきたいと思います。簡単な自己紹介と、どんな役職を担当されているかについてお話しいただきたいと思います。
石井 はい、児童養護施設れんげ学園で地域支援の担当をしています、先ほどご紹介がありましたショートステイの担当をしています石井といいます。どうぞよろしくお願いいたします。


出村 児童養護施設れんげ学園で、現在は入所している子どもたちと親御さんとの面会や、親御さんとの対応をメインでやらせていただいております、ファミリーソーシャルワーカーの出村と申します。
また、先ほどご紹介していただいた、不登校児童の居場所事業ぶらんこのコーディネイターもしております。よろしくお願いいたします。
下釜 皆さん、はじめまして。私、下釜 穣と申します。児童養護施設れんげ学園では、臨床心理士として虐待などを受けたお子さんたちの心理療法をしています。
それと、居場所支援事業ぶらんこのほうの現場スタッフもさせていただいております。よろしくお願いします。
村松 ありがとうございます。
それでは、二つ目の質問に移っていきましょう。児童養護施設では、さまざまなハードルを抱えて生活をしている子どもたちがいらっしゃいます。
そこで子どもたちと接するときに特に気を付けていることですとか、専門的な取り組みについてお話しいただきたいと思います。
出村 この業界に入って自分はもう16、7年たつんですけれども、やはり毎年のように子どもが入れ替わりまして、いろんな子どもたちと、対応をさせていただく中で気を付けることはたくさんあります。先ほどの紹介にもあったように、やはり大人との信頼関係がなくなってしまって入ってきている子たちが多いです。
また、それを見る職員たちもですね、さまざまな環境で育ってきているので、結婚されている方は分かると思うんですけれども、夫婦間でも子どもを育てるのにいろいろ感覚の差が出ると思うんですね、それがそれ以上に、40何人という職員たちがいますので、そこの感覚を合わせるのもかなり難しい状況です。
先ほどのディスカッション(ミーティングの動画)なども含めて、子どもたちにどうしていったらいいかなど、各会議などで話し合うんです。外から見たら笑えるような話なんですけれども、子どもがごはんを食べるときに「ふりかけを最初からかけていいか、それともおかわりのあとにかけるべきなのか」というような議論をまじめにやったことがあります。
ある職員は、「いや、おかわりからだろう」と。ある職員は、「ごはん食べてくれるんだったら、最初からかけていいだろう」というような形で、経済面も考えたりしながら、何が子どもたちのためになるのかを、本当に真剣に話し合ってやっていきます。
日々いろんなことについてそういう話し合いをして、この子にはこういう対応をしていくっていうようなことを、職員の中でそれをある程度ラインを設けるというのも一つ気を付けなければいけないことなのかなと思います。
下釜 続けて私のほうからですけれども、私は普段、心理職という立場ですので、先ほどの出村のように生活を直接支援する職員ではないんですね。
でも、心理職、心理士なんていうふうに聞いて、皆さん何かイメージできますでしょうか。マイナーな仕事かなと自分では思っているんですけど、結構、病院とかに勤めているカウンセラーの方とかは多いんじゃないかなと思います。
僕は、そもそも児童養護施設に来たのも一つ理由がありまして、僕は心理士として患者さんを治療するというのがどうしても、ちょっとしっくり来なくてですね、僕なんかが人さまを治療なんてできるのかと思ってですね、医療ではなくて福祉の道に来たっていうのがあります。
児童擁護施設のお子さんというのは、果たして病気でしょうかね。僕は違うと思っていて、虐待を受けてさまざまな苦しい思いをしている、それによって心の病のようなものが出てくることもあるとは思うけれども、もともとはその苦しい思いをしてきたその子がいるわけですよね。
だから、僕は子どもと関わるときに大切にしていることとしては、その子たちを治療しようとはしないことですかね。
じゃあ、どのように関わるのかということですけど、共に生きると。まさに今日のテーマになるのかもしれないんですけど、治療しよう、治そう、より良くしようとするのではなくて、その子がありのままに生きていくところを共に伴走させてもらえたらありがたいかなって。
隣にそんな人いたなって、いつか思ってくれたらいいなっていうような意識で子どもと向き合っております。

村松 ありがとうございます。
取材で何度か施設の見学をさせていただいたんですけれども、本当にお子さんたちのことを常に考えていらっしゃって、それは専門的な知識があって、そういう役職でとかではなく、全ての職員の方々が子どもたちと向き合っているのが、取材の中でひしひしと伝わってきました。
それでは、最後、三つ目の質問です。私たちであったり、この会場にお越しくださった皆さんが、そういった子どもたちに対して、どう向き合っていったらいいのか、これからの社会がどうあればいいのかに関してお話を伺いたいと思います。
石井 では、代表して石井がお答えします。
これからの社会がすべきことというところで、この児童養護施設は大きなフィールドで見ると社会福祉の制度の一つで、児童福祉法に制定された施設でございます。
この社会福祉に関して、やはり今の日本というこの国で皆さんがどれぐらい日々関心を寄せているかというところになるかと思うのですが、「福祉」とひと言で言っても、私が福祉を学んだのは 20世紀の最後、1990年代の最後で、その当時、21世紀の福祉の世界というのはおそらく日本の国は物が豊かになって、そして、そんなに生活に苦しさを感じないような、そんな時代が来るんじゃないか、その中で、やはり人と人とが関わる中、関係性の中で、そういった幸せ、それぞれの人の福祉を実現していくことが 21世紀に目指すところというようなことを私は学んだのですが、実際そのフィールドに入ってみてどうかというと、この少子化の流れの中でも児童養護施設に入所している子どもはそんなに数が変わっていません。
私がこのフィールドにいる約 28年間においてもそんなに変わっていないですし、若干増えて横ばい状況のようなところがあります。
それはなぜなのかというと、以前は戦争孤児などを受け入れていた施設に、家族がいながらも家族と離れて暮らさなきゃいけない子どもたちが増えてしまった、この社会状況にあると思います。そんな中でこれから目指すべきこの子どもたちの福祉、幸せは、やはり大切な人と共に暮らせる環境を守ってあげること、そのためには、おそらくこの自治体レベル、小さな地域で子どもを育てることを、みんなで社会化していくことが必要になってくると思います。

なので、子どもの数が少なくなってきて、なかなか子育てが身近に感じられない部分が地域の中でも出てくるかもしれませんが、そんな小さな数の子どもたちをみんなで大事に育てていって未来につなげていく、そんな意識を持つことが大事だと思っています。
なので、施設も、入所している子どもたちプラス、地域の子どもたちが入所にならないように支えていく、そんな取り組みも今進めているところです。
その一つが居場所事業ぶらんこであり、またショートステイなどの事業もこれから展開していって、子どもたちの成長を支えていきたいと思っています。ぜひ関心を持っていただけるとうれしいなと思います。
村松 ありがとうございます。私自身も今回、児童養護施設の実態について取材をする中で、こんな状況があったんだ、こんな施設があって、こういった取り組みがあるんだというのを初めて知った驚きがありました。
まずは、私たちが関心を持って歩み寄っていくことが、今回の共生についても一歩進んでいくところかなと思いました。

宮本 僕は、取材で職員の方が、「大人だから子どもには笑っていてほしい」とおっしゃっていたのが印象的で、シンプルで当たり前かもしれないけれど、優しさがあって、こういった単純な優しさがより良い共生を作っていくのではないかと思いました。
イ 私も、自分が知らなかった世界に興味を持つことから共生が生まれると思いました。その中で印象深かったのが、信頼を築いていく方法でした。今後、このことを一つの方法として取り上げ、共生していきたいと思いました。
川崎 私は、取材の中で、「もともとここに来たくて来ている子なんて一人もいない」っていう言葉をスタッフの方がおっしゃっていたのをすごく印象深く覚えていまして、自分の想像できないバックグラウンドみたいなものを相手が持っているかもしれないっていうのを、想像できないんだけど想像して接していくということがやはり大切なのかなとも思って、子どもたちだけじゃなくてそういう、日頃、人と関わるときにも生きていくことなのかなというふうに思いました。ご清聴いただきありがとうございました。
(拍手)



