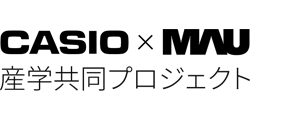
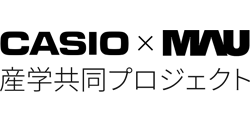
DISCUSSION 議論
PRESENTATION 発表
第2部
ひとつのテーブルの上で
– 参加者との議論 –
[司会]三代 純平
今回は「ひとつのテーブルの上で」というテーマでイベントを行っています。初めに Nadiya を取材させていただいて、食がテーマになったところからもインスパイアされていると思いますが、家族って何だろうとか、一緒に食卓を囲むって何だろうというのは、三つのチームの取材で共通していたという気がします。ウクライナから避難民を受け入れて食卓を囲むことや、杉山さんのお話でもいろいろな形で家族というものがあるのだということ、そして「れんげ」さんでも、家族ではないけれども、新しく共に生きていく共同体をつくっているなど、様々な角度で考えることができました。いろんな価値観とかいろんな背景の人が一つのテーブルに着くことは、本当に難しいと思います。ご自身の体験で、こういう部分が難しいというのがあれば、それを共有していただければと思いますし、どうすればいろいろな違いを乗り越えて共にテーブルを囲むことができるのかを、具体的な、皆さんの取り組みを紹介していただくことから始めていただいてもいいので、話し合えればいいなと思っております。

フューチャーセンターにて参加者とディスカッション
テーブル1
進行|松本 万梨
このテーブルでは、人によって正しいと感じることが違う、正義が違うことがあるという話をしました。
日本では、テストをカンニングしないっていうのが正しいことだけど、バングラディッシュでは助け合いの精神で、テストでも教え合う方が正しいと考えているそうです。
いろいろな正しさや価値観があるから、一つのテーブルにつくことは難しい。食文化でも、関東と関西で違ったりして、西の人にとっては東のうどんのだしがどうしても食べられなかったりする。とても身体的なことなので食卓を囲むのは難しいという話もありました。
それに対して、必ずしも同じ食べ物を食べる必要はなくて、お好み焼きを食べる人の隣に懐石料理を食べる人がいてもいい、大切なのは、お互いの立場を理解しようとすること、尊重することだろうという話をしました。
食べ物の好みは違いましたが、そんな食べ物の好みを、テーブルを囲んで話していたこの時間はみんな楽しむことができました。だから、会話して相互理解をするっていう一つの時間を設けるっていうことが大事なのだと思います。


テーブル2
進行|村松 智明
さまざまな世代や出身地の人と仕事をする機会が多い方たちから、日頃、自身の考えを押し付けてしまっていないかなど悩みながら接しているという声がありました。
若い時のほうが、かえってわからないことが当たり前とわりきって何でも言うことができたという方もいました。
また、どうすれば対等な関係で話をすることができるかということについてれんげ学園の石井さんから、普段から、相手を名前で呼ぶと言うこと、そして、「ありがとう」をちゃんとことばにすることを心がけているというお話がありました。
マイノリティ、マジョリティという立場の違いとどう向き合うか、価値観が衝突してしまったときどうすればいいのか、みな悩んでいます。コミュニケーションでは、1回の失敗、2回の失敗みたいなものを前提にした上で接していくことが、立場の違う人たちと理解し合うために必要なんじゃないかと考えています。
テーブル3
進行|星島 遼太郎
このテーブルでは、共に食卓を囲むことを大きく妨げる、難しくしているものとして、無関心があるんじゃないかという話がありました。
例えば同じテーブルに囲めていたとしても携帯をいじって、相手のことを見てないということが生活の中でよくあります。今日のようにお互いがお互いの顔を見て話すということが必要なのではないかという意見がでました。
また、国際交流協会に外国の方の参加が少なかったのですが、日本語だけでなく、多言語で司会をする多文化カフェというイベントをすることで参加してくれる人が増えたそうです。これについて、多言語で対応する、言語の壁を取り払ったからうまくいったということよりも、相手の言葉で対応すると言うことで、相手を受け入れる姿勢をつくったことがよかったのではないかと解釈してくれた人がいました。
そこで、やはり、他者への関心が大切だという話になりました。


テーブル4
進行|イ ダビン
最初に、どんな問題があるのか、その背景を知らなかったら食卓を囲むことは難しい、だから、そもそも関心を持つためにはどうするべきか、という話をしました。
その関心という言葉を質問という形に変えると、質問された人が、今度は、質問できるということになりまして、支援された人が支援できるみたいな、関心を持ち合う形になるのではないかという意見がありました。
またれんげ学園の出村さんから、自分たちの意見をしっかり言うには、聴いてもらった経験が大切で、それが子どもたちには不足している、だから聴くという姿勢を持つことが必要だというお話がありました。
それから、子どもたちに自ら生きていく力を付けてほしいという言葉が出て、同時に、社会として支えあうことも必要で、一人で生きていく力が強調されることへの懸念の議論もありました。自分たちに何ができるのかということを理解することが自己肯定感につながり、それを持つことで、人に頼ることもできるようになることなどが話し合われました。
テーブル5
進行|川﨑 風香
ある方から、人が違う文化へ入っていくとき、その文化に合わせた方がいいのか、それとも、その文化圏の人も新しく来る人の文化を受け入れた方がいいのか、悩むと提起がありました。
その話を巡って、善悪の話になってしまうといけない、差異なんだというところにとどめないと同じテーブルを囲みづらくなるという話が出ました。
れんげ学園の下鴨さんから、施設で子どもたちと食卓を囲むときも、いろいろな家庭から人が集まっているので、その違いを職員側が楽しめないと、子どもたちにとっても食卓が楽しいもので無くなってしまうというお話がありました。
「おまえんち、そうだったの」みたいなところから広げていって、「でも俺はこう思うんだけど、どう思う?」みたいなやりとりをやっていくことで、子どもたちが安心できる場所ができるそうです。
差異を楽しみながら、どちらかが一方的に合わせるのではなく、話し合いを重ねて、その場がみんなにとって安心できる場所にしていくことが必要なのだと思いました。


テーブル6
進行|ハン イェウン
テーブルを囲むことを難しくしているのは何かについて中心的に話し合いました。
恥ずかしい、どう見られるのか心配、自信がない、プライドが邪魔をするなどいろいろな意見が出ました。中でも、強要されるというのが一番よくないのではないかということになりました。
例えば、話をしてくださいというのも強要になるときもあるし、みんな仲良くしなければいけないというのも強要になります。強要になってしまうとつらくなる。好き嫌いもあるし、食事のペースも違う、気分によっては、一人でカウンターの隅にいて誰とも話したくないときもある。
一人一人が自由にいられることを、まずは認められる環境が必要ではないかという話になりました。その上で、お互いのことをまずは知っていくこと、例えば、LGBTQの方がどういう思いを持っているか、ということを知ることが重要だというところまで議論して時間になりました。
テーブル7
進行|イ ハリム
主に家族の中でテーブルを囲むことを難しくしていることは何かについて話し合いました。
一番は、時間をあわせるのが難しいということでした。グループには、先日、2年ぶりに独立した長男と会って一緒に食事をしたという方もしました。ただ、みんな一緒にご飯を食べると楽しいし、食べたいという気持ちも持っています。グループの一人は、大学時代からの友人と定期的に食事することにしていて、そのことが自分の心の支えになっていると話してくれました。
また、他のグループの一人は、友人が世界一周を3回しているそうですが、その友人は、おいしいものを一緒に食べればすぐに仲良くなれると言っているそうです。そして仲のいい人がその国にいれば、その国と争おうとは思わない。だから、一緒においしいものを食べる、食卓を囲むということは大切だという話を聞きました。
なかなか一緒に食卓を囲めない現代だからこそ、食卓を囲む場をちゃんとつくるということを心がけたいと思います。このテーブルのみんなで実際に食事をしたいねという話をしました。


テーブル8
進行|小川 宗之
社会の環境や価値観が変わってコミュニケーションがとりにくくなったという話をしました。
小中学校では昔と違って島を作らずに一人ずつ給食を食べることも増えたし、高校ではイヤホンをして動画を見ながら食べる人が多いそうです。
また会社でも互いに気を遣って食事に誘うこともとても少なくなったそうです。ただ、昔の、みんなでコミュニケーションをとるのがいいこと、というのも違うのではないかという話になりました。
昨年のプロジェクトで取材協力してくれたBASE298の菅根さんが、コミュニティスペースのBESE298では、みんなが一緒に囲める大きな木のテーブルと、一人ひとりが壁に向かって座れる机があるという話をされました。BASE298では、いろんな人がそこにいてもいいよっていう場所を作りたかったそうです。
だから、なんでも「駄目」じゃなくて、「いいよ」っていうふうにしてあげるといいんじゃないか、タブレットを見ながらご飯を食べるかもしれないけど、でも一緒に食べている、その空間が一番大切なんだということです。誰かといる安心感が大切だと思います。
司会|三代 純平
皆さん、ありがとうございました。
今回のテーマは「ひとつのテーブルの上で」となっていますけども、毎回このテーマを決めるのは大体 11 月の終わりぐらいに、学生たちと 90 分かけてディスカッションして決めるんですね。
自分たちの取材を振り返って、今回のテーマをどうしようかっていうのを考えて、そこでテーマが決まるとまたプロジェクトも一段進んで取材も深まっていくのですが、最後まで候補に残っていて採用されなかった言葉が、「未来」なんですね。
今回、この会場の名前がフューチャーセンターということで、すごくいいなと思って、そして高校生の方にも参加していただいて、未来に向かってこのプロジェクトが進んでいけたのではないかと思っています。
実はこのプロジェクトは今年が最後です。8 年間やってきましたけども、今年でひと区切りにしようということが決まりました。その最後の年に、高校という場所を借りて、未来に向けて話し合えたことは、私にとってはとても幸せだなと感じています。皆さん、本当にありがとうございました。



