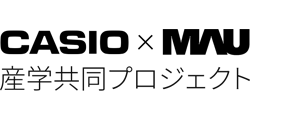
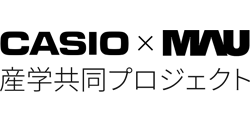
QUESTIONNAIRE 参加者の声
PRESENTATION 発表
参加者の声

高校生をはじめ若い方から人生経験豊かな方まで、また職業もさまざまな方たちと、一つのテーマで話をすること、これこそ「共生」だろうと思いました。
それぞれの発表について、テーマを掘れば掘るほど新たな疑問や壁が立ち上がってきて学生さんたちが苦労される様が伝わってきました。お疲れ様でした。個人的にはこれまで接する機会のなかった児童養護施設について知ることができたのが一番大きな収穫でした。このような場は必要ですし、それに対して何かできることがないか、考えさせられました。
このイベントが今回で一区切りというのは残念でなりませんが、「ひとつのテーブルの上で」というテーマに沿ったディスカッションが出来ました。老若男女問わずテーブルを囲む場を作っていただき、ありがとうございました。
「共生」や「対話」は最近比較的軽く言葉にしちゃうな…と振り返って反省していました。自分が「みんな」と言う言葉に含まれなかった属性や人がいることを忘れていないか、多文化共生を目指す中で難しさや困難にも向き合っていきたいなと改めて思いました。
学生のみなさんの気づきの積み重ねが、先日のあたたかい対話の場を作っていたことがとても素晴らしいと思いました!
過去にプロジェクトに参加した卒業生の方、取材先の方がたくさんいらっしゃっていたのがとても印象的でした!関わってきた方々が大事にしているプロジェクトを少しでも体験できたことがとても嬉しかったです。
ニューキャンバスの杉山さんのお話で、「家族は一番大切な他人」とおっしゃっていたのが印象的でした。自分たちは特別な家族のかたちとして取り上げられることが多いが、実際には家族の数だけいろんな種類がある、みんなそれぞれ事情が違う、というのはその通りかもしれないと思った次第です。帰宅してから、家族(夫)とこのイベントについて話をしたところ、LGBTQ に対する彼の考え方を初めて深く聞いて、家族との「考え方の違い」について知るきっかけになりました。このイベントがなかったら、このことについて話すこともなかったかもしれないので、よいきっかけとなりました。
まず、周到に準備されたこのイベントに参加できたことが光栄だと思いました。学生さんたちの発表は、インタビュー記事のまとめにとどまらず、インタビューのテーマについて自分たちがどのように考えたのか、そして私達(聴衆)はどのように考えるのか、シンプルで深いテーマを投げかけられたような気がします。参加中、ずっとぐるぐる自分の中でもいろいろと考えました。第二部のディスカッションもおもしろかったです。参加のスタンスがきちんと示されていたことも新鮮でした。無理に話さなくてもいい、聞いているだけでもいい、とはじめに言われたことで、かえって話しやすい雰囲気になったと思います。今回、私が持って帰った宿題は「中立の姿勢を守るにはどうすればよいか」(Nadiya の話から)、「他人と共に生きる、伴走するとはどういうことか」(れんげ学園の話から)です。これからも考えていこうと思います。
3つの取材対象の活動がすばらしく、且つ、学生さんたちが取材を通してそれぞれの本質に迫る言葉を引き出せていたことが印象的でした。私の中で心に残ったのは、
「食事をしましょう」…中立でいたい
「多様な家族のかたち」…家族は一番大切な他人
「子どもたちと共に生きる」…大人だから子どもには笑っていてほしい
という言葉でした。
2019 年 1月のプロジェクト発表会で、取材対象者として関わらせていただきました。そのムービー撮影の際、「あなたにとって多文化共生とは?」と問いかけられ、自分の中でしっくり来る答えを出せませんでした。自分でインタビューに答えながら「きれいごと言ってるな」と自分の言葉につっこみを入れている自分がいました。それは、私の中で「多文化共生」に対する違和感があったからです。その違和感は、マジョリティ側である日本人が、マイノリティである在日外国人に対して「私たちの文化に迎え入れますよ。私たちは寛容ですよ。多文化共生ですよ。」と言いながら、実際には寛容ではないという現実を見てきたから生まれた違和感でした。この多文化共生プロジェクトは、ここ数年は日本人と外国人という枠を超えて、様々な人間の在り方や生き方に焦点を広げてきました。今回のプロジェクトは、その意味でも集大成として秀逸だったと思います。「共生」の本質を考える視座に迫っていたのではないかと思います。今回のイベントを経て、私が6年前のインタビューのときと同じように「あなたにとって多文化共生とは?」と問われたら、私は「他者の幸せを願うこと。」と答えるな、と思いました。この言葉はいまの自分にはしっくり来ています。とても難しいことだからこそ、追い続けていきたいと思います。
対話は労力が必要なことです。だからこそ見えることがあり、大切なことだとは重々わかっていても、余裕がないときや意見の違いがありそうなときは、避けようとしてしまうこともあります。しかし、今回のイベントに参加して、言葉にして伝え合うことの重要さをあらためて思い出しました。ちょうど個人的にモヤモヤしていたことがあったのですが、ミーティングの場を設定し、互いに思っていたことをしっかりと話し合い、スッキリすることができました。今回のイベントに関わっていた皆さんが真剣に「コミュニケーションをとること」に向き合っていたことに背中を押してもらったと思っています。
取材先の方の言葉、それを受けて考えた武蔵野美術大学の学生さんたちの言葉、その後のディスカッションで参加者の方々が聞かせてくれた言葉に、はっと気づかされたことがたくさんあり、自分を振り返る機会になりました。ディスカッションのグループの皆さんが本当に穏やかで、傾聴の姿勢をもっていらしたことも印象的で、それぞれの立場や経験は違っても、「このひとつのテーブルを囲もうとしている」という雰囲気が非常に心地よかったです。「対話のルール」が共有できていたこともありますし、ファシリテーターのダビンさんの落ち着いた雰囲気も、そうさせてくれたように思います。こういう雰囲気はどうやったら作れるだろう…と引き続き考えています
みんなで足並みを揃えて社会を変えていくことは難しいので、気付いた人が気づいた時に始めるというのが大切なのだと思いました。例えば自分が羞恥心を捨てて話せば相手も少し心を開いてくれるかもしれない。これは他者や自分以外の世界を知るきっかけになります。知ろうとすることや、知ってもらうことを私たちから始めていき、その行為が人から人へ繋がるよう意識してみる。ささやかですが自分のできそうなことを発見できました。貴重な機会をありがとうございました。
「テーブルを囲む」という状況にも多様性があるということに気がつきました。一緒にご飯を食べていなくてもいい、スマートフォンをいじっている人がいてもいいし、話を聴いていなくてもいい、ただテーブルに一緒に座っているということ自体にも意味があるのだと改めて気づかされました。
一つの言葉・テーマに対するアプローチ方法ってほんと様々なんだなということを改めて気づきました。自分は過去に「地域愛・地元愛(愛着)」という言葉に向き合いながらプロジェクト活動をしている時期があります。その時も、この言葉をどういう切り口で、どういった視点から観察してアプローチしていくのかをものすごく思考し、他者と対話していました。そこで今回のイベントでは、「共生」という言葉をテーマに 3 つのプレゼンテーションを聞いて、改めて言葉からアプローチできる視点の広さについて考えさせられました。



